
祝い肴三種
田作りは、関東の祝い肴三種(いわいざかなさんしゅ)の一つです。
祝い肴三種とは、代表的な3つのおせち料理で、
この3つが揃えばおせちの形が整うと言われています。
地域によって祝い肴三種が異なっており、
関東では、黒豆、数の子、田作り
関西では、黒豆、数の子、たたきごぼう
の三料理を指しています。
田作りの語源
田作りは、カタクチイワシの稚魚を乾燥させて、砂糖・醤油・みりんを絡めて炒ったものをいいます。
いわしを田んぼの肥料として使用したら、五万俵もの豊作になったことから、
田を作る、すなわち『田作り』と呼ばれるようになりました。
田作りの言われ
この由来から、田作りの別名「ごまめ」の当て字として、「五万米」と書かれるようになり、
おせち料理として田作り(ごまめ)は、五穀豊穣の願いが込められるようになりました。
更に、稚魚を多く使用することから、子宝に恵まれるという言われもあり、
子孫繁栄の意味としても、縁起がいいとされています。
田作りとごまめの違い
「田作り」と「ごまめ」の違いについて、現在ではほとんど同じ料理を指しますが、由来は少し異なります。
ごまめは、戦国時代半ばから登場し、「ごまめの歯ぎしり」や「ごまめの魚交(ととま)じり」といった慣用句から
卑近な表現として使われていました。
一方、「田作り」は江戸時代初期にが登場し、語源通り当初からお正月料理の一つとして食されていました。
語源や由来は異なりますが、料理自体は同じものを指すので、
現在ではおせち料理の呼称として「田作り」、一般的な料理の呼称として「ごまめ」と
使い分けるのが正しいかもしれまんせんね。
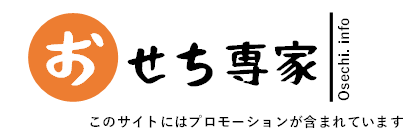


コメント